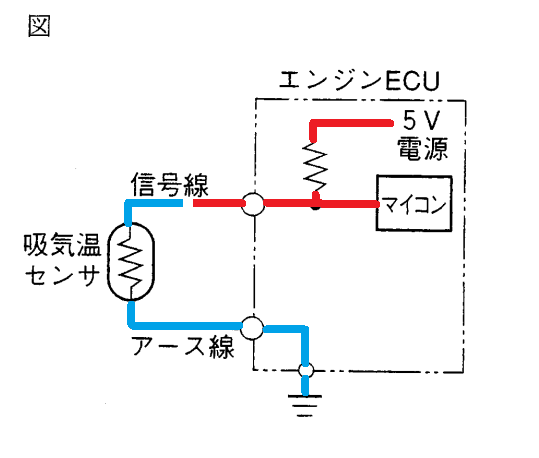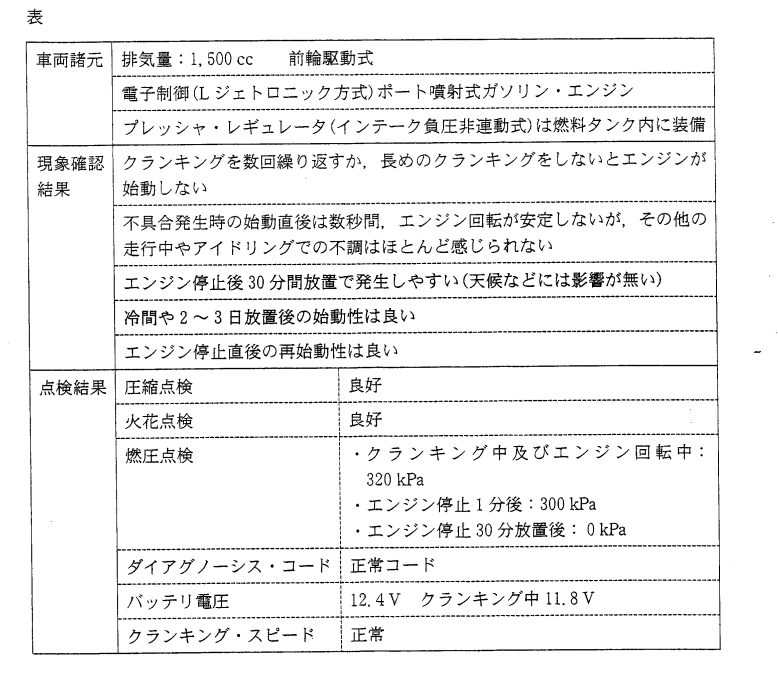34
EPSに関する次の文章の(イ)~(ハ)にあてはまる語句の組み合わせとして,適切なものは次のうちどれか。
『アシスト・モータ出力制限制御は,極端に連続して据え切りを行った場合などに,アシスト・モータの出力を制限し,(イ)から(ロ)を保護する制御である。この制御が行われた場合,警告灯は(ハ)。そのため,「操舵力が重い」という不具合を故障探求する場合は,発生条件を十分問診する必要がある。』
|
(1)(イ)異常加熱 (ロ)アシスト・モータ (ハ)点灯する
|
|
(2)(イ)異常加熱 (ロ)システム (ハ)点灯しない
|
|
(3)(イ)異常電圧 (ロ)アシスト・モータ (ハ)点灯しない
|
|
(4)(イ)異常電圧 (ロ)システム (ハ)点灯する
|
解く
『アシスト・モータ出力制限制御は,極端に連続して据え切りを行った場合などに,アシスト・モータの出力を制限し,(イ異常加熱)から(ロシステム)を保護する制御である。この制御が行われた場合,警告灯は(ハ点灯しない)。そのため,「操舵力が重い」という不具合を故障探求する場合は,発生条件を十分問診する必要がある。』
よって答えは(2)
(2)(イ)異常加熱 (ロ)システム (ハ)点灯しない
モータ出力制限制御
モータ出力制限制御は,連続した大電流での発熱からシステムを保護する制御である。
据え切り連続などのステアリング操舵を極端に繰り返したときは,モータ電流を低下させ,システムを保護している。
この制御が行われると,補助動力が徐々に低下する。補助動力の復帰は,操舵トルクがゼロ又は,イグニション・スイッチOFFから徐々に始まり,通常の補助動力に戻るのは最長で8分程度必要とする。
補助動力の制限
据え切り操作を極端に連続して行うようなときには,モータ電力が増大してECUが発熱し、システムに悪影響を及ほすことが予想できる。このため,モータ電流を監視しており,発熱状態のときは,補助動力を徐々に低下させてシステムの保護を行っている(モータ出力制限制御)。このとき,EPS警告灯は点灯しない。なお,復帰には最長で8分程度を必要とするので考慮する。